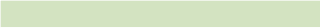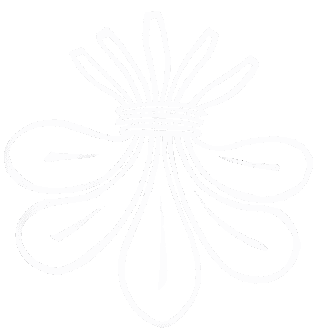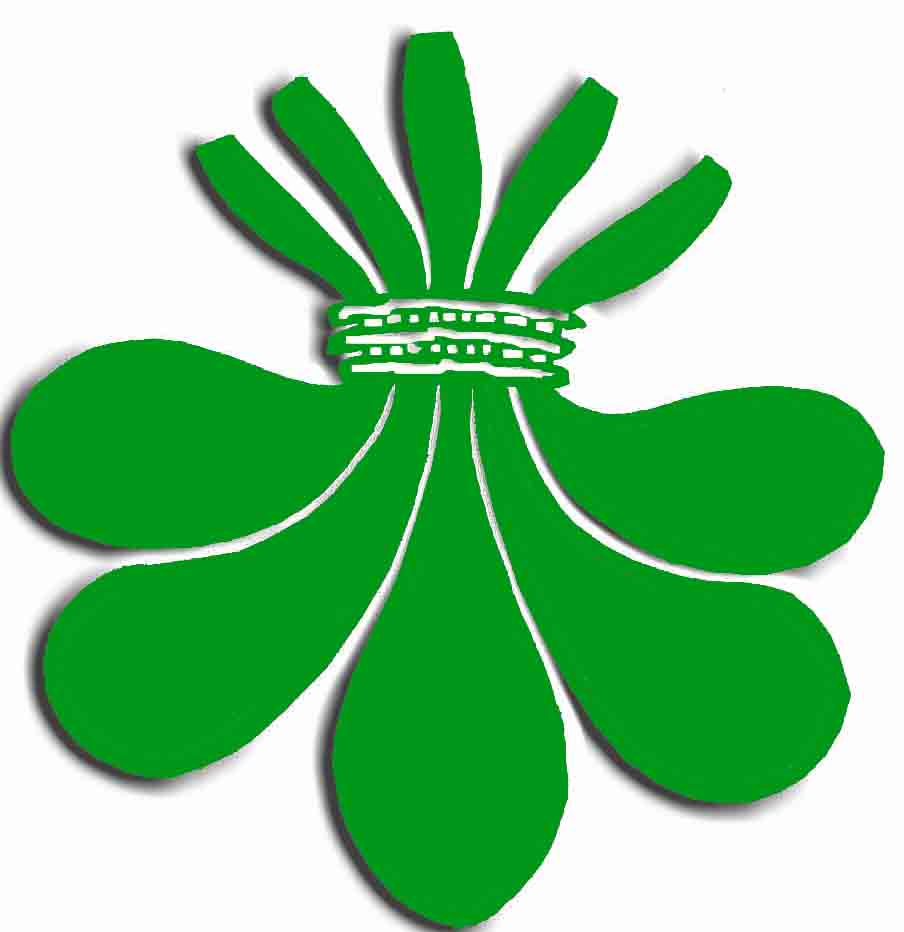照子さん2.【認知症】
=ep6=
「認知症」この言葉は、「認知症」を発症している本人は、きらいな言葉。というより他人事。本人は「少しばかり物忘れが多くなった」と思っているだけ。
家族は「認知症」を患った身内に対して、どうすべきか戸惑い「しっかりして」と強い言葉で、責めてしまう。本人は、訳も分からず怒られていると認識している。怒られたことも「悲しい事」ますます「認知症」が悪化していく。
「役に立たず、怒られてばかり」「皆と話が合わず楽しくない」「将来が不安」などの「悲しい」「寂しい」「不安」が「認知症」悪化に関わっていないかな?と母を見ていて、そう思う。
80歳を超えた頃、耳が遠くなってきた事も一因ではあるが「おばあちゃん、おばあちゃん」と言って、いつもそばにいた小さな孫たちが大人になり、家族間の会話についていけなくなったあたりから母の「認知症」が始まってきた気がする。家族が多いから寂しくないだろうと考えていたが、逆に「大勢の中の孤独」では? そう思った私は、3週間に一度は戻り、話題を作り「笑ってもらう」ことに努力した。 耳が遠くなった母と叔父が、かみ合わない話をしながらも、楽しそうに「会話?」してるのを見て、会話が必要と感じたからだ。あと家族には「注意や世話を焼く」時は、声も小さめでとお願いした。
兄が大きな声を出しただけで、「お父さんに叱られた」と子供のように「しゅん」としていたから。声が大きいだけで「怒られた」と思ってしまうようだ。
だからといって、子供扱いは要注意。子供のような扱いで、自分の世話を焼き始めた孫をうとましく思うような態度が出はじめた。今まで世話を焼いてきた子供たちに、子供扱いされることは許せない様だ。
家族の協力のおかげで「認知症」の悪化が緩やかになってきた。
が、その後、お昼二人きり(一人と1匹)だった芝犬「こころちゃん」が死んだ時は、毎日泣いてばかりで意識も、もうろうとし始めた。「寂しさ」が増したようで身体も脳も少し「悪化」。しかし約半年後、保護犬「愛之助」がやってきた。そしたら変化が・・。
この「愛之助」少しおっちょこちょいで、何かと「笑わせてくれる」それが功を奏してか93歳になった今の母は、身体も脳も少し「回復」。よく笑うようになった。おかげで寝たきりにならず、お昼はやはり二人きり(一人と1匹)でお留守番してくれてる。笑う事は大切なんだなあと感じる。
又、他の人が笑っているその輪に入れない寂しさは、計り知れない事もわかってきた。 2024-02記述
 ep.へ
ep.へ

緑文化普及協会
〒470-0113 愛知県日進市栄2丁目604「てるかガーデンデザイン」内
TEL:0561-72-7787
TOPへ戻る
ページ先頭に戻る
緑文化が出来ること
=ep6=
よもやま話
tomoe エッセイ
Ⅲ.1世紀前に生まれた女の子の話】
=直に100歳になる母の話=
■「土を育てる」
=伝えること=



 ep.へ
ep.へ