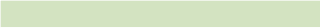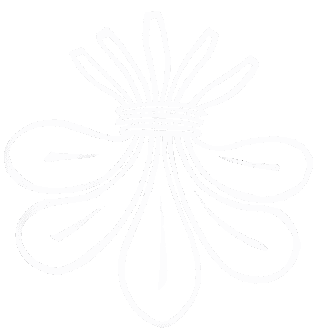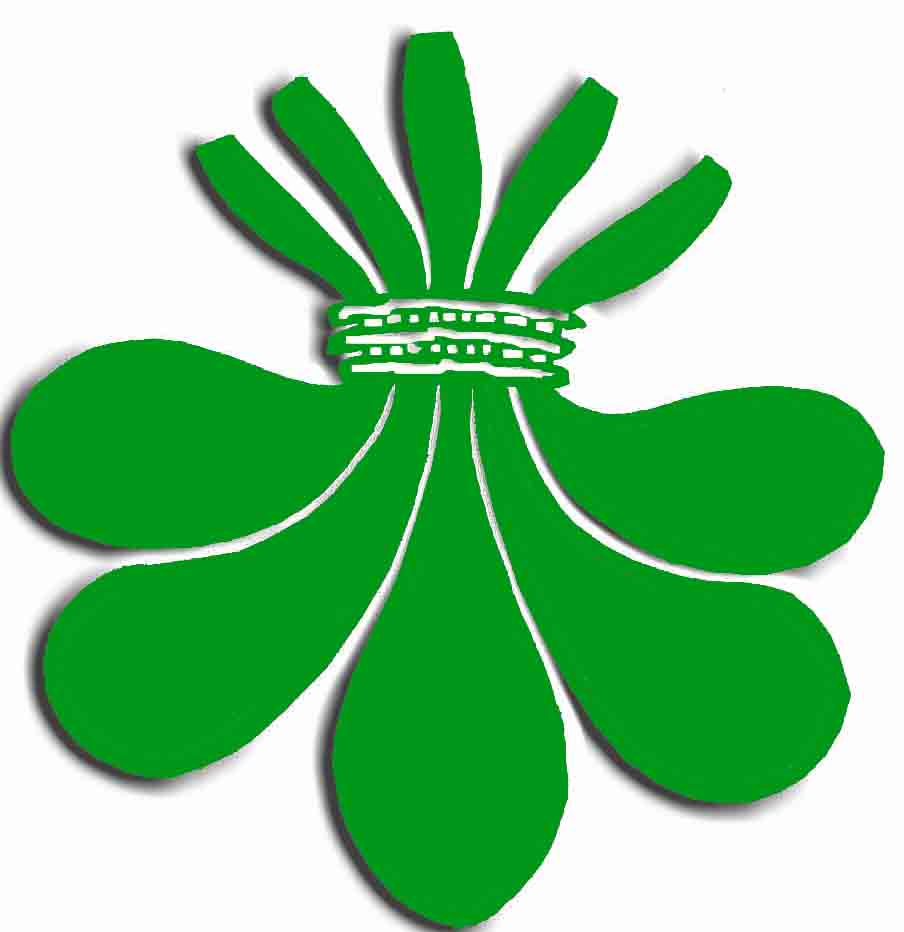これまで緑化があれば、 CO2の吸収に役立つとだけ思ってきた。土壌の中のCO2の事は、あまり考えてこなかった。生きた土(微生物の多い土)が、植物を元気に育てることは、肌で感じてきた。 そのために庭に植栽をする際、生きた土が多くなればと思い、化成肥料や農薬を避け、堆肥やもみ殻燻炭を漉き込んできた。その時、良い事だと思い、体力の限界まで、土壌をひっくり返し(天地返し)てきた。
だが、なんと、それは間違っていた。
確かに、微生物の食料となる「堆肥」や住処を作る「炭」などを土中に漉き込む事は、有用ではある。が、土をかき乱すことが、土中の微生物の住処を崩すことになることに、気が付いていなかった。微生物に住処(根圏)があることも・・・。
そして、根の中の微生物と根の共存にも、気が付いていなかった。植物の根が土中にあることで、微生物も植物も育つという、共存体であるということも・・・。
そういえばこの仕事を始めた頃、マザーポットに植え込んだ弱った「さつき」は、ポット内の土をかき回すことが出来ないので、ダメもとでポットの足元に「生ごみを堆肥にしたもの」を「さつき」の足元に乗せたことがあった。
小さな場所の上に乗せるだけでは、たいした効果は得られないだろうと思っていた。が、数か月後、傷んで黄色くなっていた「さつき」は、緑色の葉をふさふさと、つけ始めた。
その時も、まさか、あの「労力も要さない施肥」が効果をあげていたとは思っていなかった。しかし今思えば、化成肥料だけの時とは違い、目に見えて「さつき」が生き生きしてきたことは、覚えている。
最近「カーボンファーミング」というTVを見て、「目からうろこ」。その後、関連本も読みまくった。
土壌の「根圏」を残すことで、植物が吸収したCO2を土の中に固定する。そして従来の土をかき回す工法は、CO2を排出するばかりだという内容。
本当の自然農(無農薬・無肥料・微生物との共存)の世界を知った。
長い間、土壌の天地返しや、何も植えず、土壌を休ませる農業の方法が「地球に良いことをしている」と思い込んできたことが悲しい。
世界中の「化成肥料漬け」の大規模農家が、大気中のCO2を大地に戻していく事を実行することが出来るのであれば「明るい未来」を実現できる。
幼い頃眺めていた、収穫後の田んぼに、「レンゲ」が咲く美しい風景を、もう一度見てみたい。
私も緑化を職業としているので、小さい面積ながらも、今後は、微生物の住処を意識し、少しでもCO2の回収をしていきたい。 2024-01記述
 ep10「ゴミ処理問題」に続く
ep10「ゴミ処理問題」に続く
緑文化普及協会
〒470-0113 愛知県日進市栄2丁目604「てるかガーデンデザイン」内
TEL:0561-72-7787
TOPへ戻る
ページ先頭に戻る
緑文化が出来ること
明るい未来 1. 【土中環境】
=ep2=
よもやま話
tomoe エッセイ
=ep2=
Ⅱ.微生物と明るい未来
=主に微生物の話=
■「土を育てる」
=伝えること=


 ep10「ゴミ処理問題」に続く
ep10「ゴミ処理問題」に続く